2014年05月31日
禅系宗派の文化・しきたり㉕
平安時代になると、比叡山や高野山のような山岳地帯につくられたため、不規則な伽藍配置になります。
そして鎌倉時代以降は、中国から禅が伝わったことによって禅宗様という中国風の形式がさかんになりました。
禅宗様の先鞭となったのが、一二五三年(建長五年)に建てられた建長寺です。開山したのは北条時頼に招かれた宋の禅僧・蘭渓道隆で、中国臨済宗の名刹・万福寺を模した当時最新の形式でした。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり㉖にて)

そして鎌倉時代以降は、中国から禅が伝わったことによって禅宗様という中国風の形式がさかんになりました。
禅宗様の先鞭となったのが、一二五三年(建長五年)に建てられた建長寺です。開山したのは北条時頼に招かれた宋の禅僧・蘭渓道隆で、中国臨済宗の名刹・万福寺を模した当時最新の形式でした。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり㉖にて)

2014年05月31日
初イカ釣り!(^^)!
おはようございます(^o^)丿
連日暑い日が続いている伊万里地方です^_^;
さて、最近始めたイカ釣り。エギングを年に数回していたのですが、未熟なため一回も釣れたことがありませんでした(*_*)
そんな話を知り合いの方としていたら「ヤエンばしてみるね」と誘っていただき、是が非でも初一匹を釣りたかったので早速行ってきました(*^_^*)
そして・・・
おかげさまであげてきました水イカ!(^^)!

釣果は水イカ2、コウイカ1の大釣果ヽ(^。^)ノ
久々にMaxハイテンションになりました(^ム^)
帰って食したら過去一美味しかったです(^-^)
イカ釣り、ハマりそうです(^0_0^)
連日暑い日が続いている伊万里地方です^_^;
さて、最近始めたイカ釣り。エギングを年に数回していたのですが、未熟なため一回も釣れたことがありませんでした(*_*)
そんな話を知り合いの方としていたら「ヤエンばしてみるね」と誘っていただき、是が非でも初一匹を釣りたかったので早速行ってきました(*^_^*)
そして・・・
おかげさまであげてきました水イカ!(^^)!

釣果は水イカ2、コウイカ1の大釣果ヽ(^。^)ノ
久々にMaxハイテンションになりました(^ム^)
帰って食したら過去一美味しかったです(^-^)
イカ釣り、ハマりそうです(^0_0^)
2014年05月30日
禅系宗派の文化・しきたり㉔
寺院は建てられた時代、属する宗派によって建物の配置やつくりが異なります。
日本ではじめて寺院が建てられたのは、奈良時代のことです。寺院の建物を伽藍といいますが、当時の伽藍配置は金堂と塔が中心でした。法隆寺式・薬師寺式・東大寺式・飛鳥寺式などが代表例です。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり㉕にて)

日本ではじめて寺院が建てられたのは、奈良時代のことです。寺院の建物を伽藍といいますが、当時の伽藍配置は金堂と塔が中心でした。法隆寺式・薬師寺式・東大寺式・飛鳥寺式などが代表例です。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり㉕にて)

2014年05月29日
禅系宗派の文化・しきたり㉓
本格的な枯山水庭園は、臨済宗の禅僧・夢窓疎石が一四世紀につくった西芳寺の庭園にはじまります。またこの頃つくられたものとしては、大仙院の方丈東庭、龍安寺石庭、妙心寺退蔵院方丈西庭などがよく知られています。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり㉔にて)

(続きは、禅系宗派の文化・しきたり㉔にて)

2014年05月29日
久々の大台突破ヽ(^。^)ノ
おはようございます(^O^)/
夏のような日差しが続いている伊万里地方です(*^。^*)
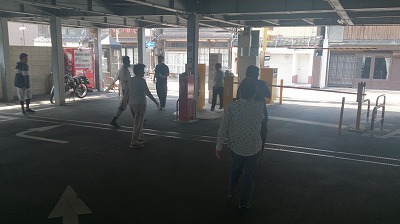
約3年近く続けている朝のラジオ体操、本日は久々に10名の参加者でにぎやかに体を動かしてきました(^^♪
おかげさまで明るく元気に朝を迎えることができています!(^^)!
8時40分よりいすい通商店街いすいパーキング前にておこなっておりますので、一緒に心と体の調子を整えませんか(^0_0^)

さぁ、本日も1日明るく元気に張り切って頑張っていきましょうヽ(^。^)ノ
夏のような日差しが続いている伊万里地方です(*^。^*)
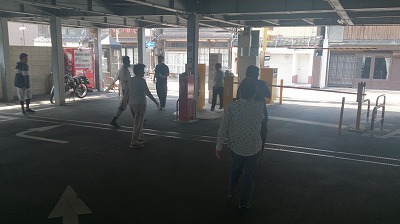
約3年近く続けている朝のラジオ体操、本日は久々に10名の参加者でにぎやかに体を動かしてきました(^^♪
おかげさまで明るく元気に朝を迎えることができています!(^^)!
8時40分よりいすい通商店街いすいパーキング前にておこなっておりますので、一緒に心と体の調子を整えませんか(^0_0^)

さぁ、本日も1日明るく元気に張り切って頑張っていきましょうヽ(^。^)ノ
2014年05月28日
禅系宗派の文化・しきたり㉒
この自由な見方が、すべてのこだわりを捨て、あるがままに生きることを目指す禅の精神に通じるのです。
じつは禅寺の庭に大きな影響を与え、枯山水庭園として発達させたのは、禅とともに日本に入ってきた宋・元の時代の水墨画だといいます。墨一色で風景を描ききる水墨画は、禅の境地と同じであったからです。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり㉓にて)

じつは禅寺の庭に大きな影響を与え、枯山水庭園として発達させたのは、禅とともに日本に入ってきた宋・元の時代の水墨画だといいます。墨一色で風景を描ききる水墨画は、禅の境地と同じであったからです。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり㉓にて)

2014年05月28日
アンパンマンミュージアム(*^。^*)
来週から6月、夏の足音が日々大きくなってきてる感じですね(*^_^*)
今から8月15日までは繁忙で、休みをとって遠方に行く機会がなかなか無いので、娘を連れて行ってきましたアンパンマンミュージアムヽ(^。^)ノ

以前から楽しみにしていたみたいで、入場前からテンションMax!(^^)!
アンパンマンショーでさらにアゲアゲでした(*^_^*)

アンパンマン号でもはしゃぐ(^^♪

走り回って遊んで記念写真も撮れて良い思い出になったみたいです(´・ω・`)


パパも充電OK!(^^)!
お盆終了まで元気いっぱい仕事に励みたいと思いますヽ(^。^)ノ
今から8月15日までは繁忙で、休みをとって遠方に行く機会がなかなか無いので、娘を連れて行ってきましたアンパンマンミュージアムヽ(^。^)ノ

以前から楽しみにしていたみたいで、入場前からテンションMax!(^^)!
アンパンマンショーでさらにアゲアゲでした(*^_^*)

アンパンマン号でもはしゃぐ(^^♪

走り回って遊んで記念写真も撮れて良い思い出になったみたいです(´・ω・`)


パパも充電OK!(^^)!
お盆終了まで元気いっぱい仕事に励みたいと思いますヽ(^。^)ノ
2014年05月27日
禅系宗派の文化・しきたり㉑
しかし鎌倉時代後期から室町時代になると、仏教庭園は変化を見せます。山や水をいっさい廃した枯山水が登場したのです。
禅寺の枯山水庭園は白砂と石組だけの空間で、水を用いずに山やせせらぎ、大海に浮かぶ島々などの風景をあらわしています。
池で遊ぶことも散策することもできませんが、枯山水を見る人はそれぞれの発想で庭と向き合い、ついには自分を見つめなおして無の境地になろうとします。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり㉒にて)

禅寺の枯山水庭園は白砂と石組だけの空間で、水を用いずに山やせせらぎ、大海に浮かぶ島々などの風景をあらわしています。
池で遊ぶことも散策することもできませんが、枯山水を見る人はそれぞれの発想で庭と向き合い、ついには自分を見つめなおして無の境地になろうとします。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり㉒にて)

2014年05月26日
禅系宗派の文化・しきたり⑳
平安時代から鎌倉時代にかけての仏教庭園は、当時さかんだった浄土信仰の影響で極楽浄土のようすを表現した浄土庭園が多く、大きな池や山、草木が華麗に配されていました。貴族たちが財を競ってつくったこの庭園では、遊興・散策を楽しむことも可能でした。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり㉑にて)

(続きは、禅系宗派の文化・しきたり㉑にて)

2014年05月26日
子供の成長(*^_^*)
昨日は長女が通っている保育園の運動会でした(*^_^*)
1年前、初めての運動会の時はママから離れず競技に参加するのも一苦労でしたが、1年が経ち保育園にも慣れ友達と元気よく走り回っていました(*^。^*)

明るく元気に競技に参加している娘を見て、成長を感じた楽しい1日でしたヽ(^。^)ノ
1年前、初めての運動会の時はママから離れず競技に参加するのも一苦労でしたが、1年が経ち保育園にも慣れ友達と元気よく走り回っていました(*^。^*)

明るく元気に競技に参加している娘を見て、成長を感じた楽しい1日でしたヽ(^。^)ノ
2014年05月25日
禅系宗派の文化・しきたり⑲
塀に囲まれた庭には木も草も水もなく、あるのは白砂と石組だけ・・・。そんな禅寺の枯山水庭園を見て、いったい何をあらわしているのかと不思議に思ったことはないでしょうか。
仏教庭園の起源は、古代インドの神話に出てくる須弥山にあるといいます。須弥山は世界の中心にそびえる高い山で、仏教の宇宙観を表現したものです。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり⑳にて)

仏教庭園の起源は、古代インドの神話に出てくる須弥山にあるといいます。須弥山は世界の中心にそびえる高い山で、仏教の宇宙観を表現したものです。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり⑳にて)

2014年05月24日
禅系宗派の文化・しきたり⑱
禅の世界では、書を「有声の画」とよびます。何かを語りかけてくる絵のようだという意味です。書によって、あるがままの禅の精神をとらえることができるのです。
いっぽう、「無声の詩」とよばれるのが禅画です。禅画には師の肖像を描いた頂相や前衛的な禅機画、墨の濃淡で自然の風景をあらわす山水画などがあり、どれも禅の奥深さを感じさせます。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり⑲にて)

いっぽう、「無声の詩」とよばれるのが禅画です。禅画には師の肖像を描いた頂相や前衛的な禅機画、墨の濃淡で自然の風景をあらわす山水画などがあり、どれも禅の奥深さを感じさせます。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり⑲にて)

2014年05月24日
2014年盆提灯(*^_^*)
おはようございます(^O^)/
夏日が続いている伊万里地方です(*^_^*)

7月盆まで2ヶ月をきり、お盆商品の季節が到来しました(*^。^*)
当店では、2014年最新の盆提灯から定番のものまで様々な商品を展示いたしております。




実際にご覧になり、比較しながらご検討いただけるよう展示しておりますので、お気軽にお立ち寄りください(^◇^)
皆様のご来店を心よりお待ちいたしておりますヽ(^。^)ノ

夏日が続いている伊万里地方です(*^_^*)

7月盆まで2ヶ月をきり、お盆商品の季節が到来しました(*^。^*)
当店では、2014年最新の盆提灯から定番のものまで様々な商品を展示いたしております。




実際にご覧になり、比較しながらご検討いただけるよう展示しておりますので、お気軽にお立ち寄りください(^◇^)
皆様のご来店を心よりお待ちいたしておりますヽ(^。^)ノ

2014年05月23日
禅系宗派の文化・しきたり⑰
元が日本を襲撃した文永・弘安の役が終わると、元の禅僧も来朝するようになり、また日本の禅僧も入元して、宋・元の書風をもたらしました。
この頃の禅僧でとくに知られているのは、一山一寧です。彼は後宇田法皇の要請で南禅寺に入りました。これにより、禅と宋・元の文化は貴族階級にも広まることとなりました。一山は詩文と書にすぐれ、その影響で禅寺では書がさかんに行われました。この時代の禅僧は、技巧や書法にこだわらず、あるがまま自由に書きました。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり⑱にて)

この頃の禅僧でとくに知られているのは、一山一寧です。彼は後宇田法皇の要請で南禅寺に入りました。これにより、禅と宋・元の文化は貴族階級にも広まることとなりました。一山は詩文と書にすぐれ、その影響で禅寺では書がさかんに行われました。この時代の禅僧は、技巧や書法にこだわらず、あるがまま自由に書きました。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり⑱にて)

2014年05月22日
禅系宗派の文化・しきたり⑯
その後は、大陸で元が興ったことによって、書の歴史が大きく変わりました。一二七九年(弘安二年)に、南宋が元に滅ぼされると、混乱のなかで蘭渓道隆・無学祖元・一山一寧などの亡命僧が日本に逃れてきました。来日した宋僧たちはみな書に優れていたため、日本では宋風の書を尊重するようになりました。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり⑰にて)

(続きは、禅系宗派の文化・しきたり⑰にて)

2014年05月21日
禅系宗派の文化・しきたり⑮
日本で書がもっとも盛んだったのは、三筆や三蹟とよばれる人たちが活躍した平安時代です。この頃は中国風の優麗な書が書かれていましたが、鎌倉時代になると、武士の台頭で書も力強い作風になります。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり⑯にて)

(続きは、禅系宗派の文化・しきたり⑯にて)

2014年05月20日
禅系宗派の文化・しきたり⑭
室町時代に花開いた禅文化は日本のさまざまな文化に影響を与えましたが、書道もまた禅の影響を強く受けています。禅僧には、書道が修行の一つとされるほどでした。
禅僧の名筆は、臨終の句である遺偈や悟りの境地を記した偈頌、悟ったことを証明する印可状などに見られます。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり⑮にて)

禅僧の名筆は、臨終の句である遺偈や悟りの境地を記した偈頌、悟ったことを証明する印可状などに見られます。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり⑮にて)

2014年05月19日
禅系宗派の文化・しきたり⑬
武道では、心の状態が勝敗を左右するので、精神統一が重視されます。相手の動きに対しては反射神経が研ぎ澄まされていなければならないし、恐怖心や邪念にとらわれていては、瞬間的に反応することができません。集中力と、何ものにもとらわれない自由な精神が必要になるのです。
そのために意識を一点に集中させる坐禅の瞑想法が必要とされました。武道家たちは瞑想で集中力を養い、それぞれの道を極めようとしたのです。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり⑭にて)

そのために意識を一点に集中させる坐禅の瞑想法が必要とされました。武道家たちは瞑想で集中力を養い、それぞれの道を極めようとしたのです。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり⑭にて)

2014年05月19日
第1回伊万里にぎわいマルシェin伊万里玉屋
おはようございます(^O^)/
快晴が続き暑い日が続いている伊万里地方です(*^_^*)

昨日5月18日(日)伊万里玉屋大駐車場で開催いたしました第1回伊万里にぎわいマルシェ、おかげさまで大盛況のなか無事に終了いたしました(^0_0^)

ご来場いただきました皆様、誠にありがとうございました!(^^)!
毎月第3日曜日(6月は15日日曜日)午前9時~午後2時伊万里玉屋大駐車場にて開催しておりますので、次回も宜しくお願い申し上げますヽ(^。^)ノ

快晴が続き暑い日が続いている伊万里地方です(*^_^*)

昨日5月18日(日)伊万里玉屋大駐車場で開催いたしました第1回伊万里にぎわいマルシェ、おかげさまで大盛況のなか無事に終了いたしました(^0_0^)

ご来場いただきました皆様、誠にありがとうございました!(^^)!
毎月第3日曜日(6月は15日日曜日)午前9時~午後2時伊万里玉屋大駐車場にて開催しておりますので、次回も宜しくお願い申し上げますヽ(^。^)ノ

2014年05月18日
禅系宗派の文化・しきたり⑫
剣の道は人を殺傷しかねない道であり、禅の道は悟りを開くことによって自己を活かす道です。一見、正反対の道ですが、沢庵はその著書の中で「通達の人は刀を用いて人を殺さず、刀を用いて人を活かす」と説いています。
つまり剣の達人は刀で人を斬ることはなく、気迫にのまれた相手が身動きできなくなってしまうから、思うがままに操れると教えているのです。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり⑬にて)

つまり剣の達人は刀で人を斬ることはなく、気迫にのまれた相手が身動きできなくなってしまうから、思うがままに操れると教えているのです。
(続きは、禅系宗派の文化・しきたり⑬にて)








