2011年04月05日
ネット環境整いました♪
今まで、実家兼職場のパソコンからアクセスしていたのですが、昨日からようやく我が家にもインターネットをできる環境が整いました♪
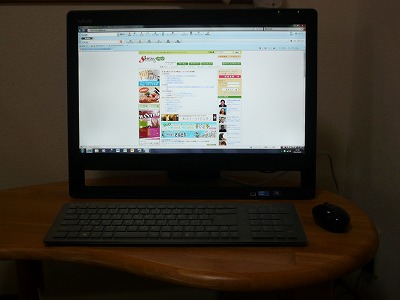
マニュアルを読めば何とかなるだろうと思い、インターネット接続設定及び無線LANに初挑戦!
最初の設定時はLANケーブルが必要なことを知らず、サービスセンターに電話したりマニュアルを穴が開くほど見るも繋がらず(泣)
悪戦苦闘の末、6時間後なんとかインターネット接続&無線接続に成功(^o^)丿
何事も経験が必要だなと感じた一日でした。
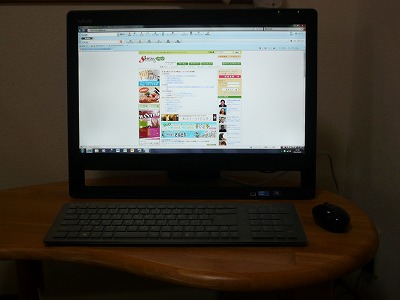
マニュアルを読めば何とかなるだろうと思い、インターネット接続設定及び無線LANに初挑戦!
最初の設定時はLANケーブルが必要なことを知らず、サービスセンターに電話したりマニュアルを穴が開くほど見るも繋がらず(泣)
悪戦苦闘の末、6時間後なんとかインターネット接続&無線接続に成功(^o^)丿
何事も経験が必要だなと感じた一日でした。
2011年04月05日
提灯を贈るとき、何を基準に贈ったらいい?
◎提灯を贈るとき、何を基準に贈ったらよいか?
自分の好みではなく、先様のご都合に合わせた方がよいと考えます。
初盆の贈答品の場合が多いですが、ご自身の予算と先様の都合を考えて広い仏間のあるお家には大きめのものを、狭いお家には小さめの置き提灯、または空間利用で御殿丸等を贈ると喜ばれるのではないでしょうか。
銘木か蒔絵にするか、置きちょうちんにするか釣ちょうちんにするか、大内行灯か廻転行灯かと決まった基準は特にないので、自分の好みではなく先様の事情や好みに合わせて選ばれると良いでしょう。
自分の好みではなく、先様のご都合に合わせた方がよいと考えます。
初盆の贈答品の場合が多いですが、ご自身の予算と先様の都合を考えて広い仏間のあるお家には大きめのものを、狭いお家には小さめの置き提灯、または空間利用で御殿丸等を贈ると喜ばれるのではないでしょうか。
銘木か蒔絵にするか、置きちょうちんにするか釣ちょうちんにするか、大内行灯か廻転行灯かと決まった基準は特にないので、自分の好みではなく先様の事情や好みに合わせて選ばれると良いでしょう。
2011年04月05日
提灯はいつの時代からあるの?
◎提灯はいつの時代からあるの?
900年前の平安末期に発生し、庶民が本格的に使用し始めたのは江戸時代以降のことです。
中国から渡来したのか、日本で創られたものなのか定かではありませんが、日本で一番古い提灯の文献は応徳2年「朝野郡載」に見えてきます。(900年前の平安末期)
江戸時代以前の提灯は主として天皇家・貴族・武家・僧侶の上流階級で使用され、本格的に庶民が宗教的儀式のお盆や日常生活の照明器具として使い始めたのはローソク(従来は油)が大量生産になって安く入手できるようになった江戸時代以降のようです。
上流階級の提灯の使い方は、従来の松明に替わって紙と木の覆いをつけた灯台、あんどんのように実用品としても使っていましたが、多くは宗教的祭礼や儀式として石灯籠・釣灯籠・切子灯籠を仏前に供える献灯具となっていました。
900年前の平安末期に発生し、庶民が本格的に使用し始めたのは江戸時代以降のことです。
中国から渡来したのか、日本で創られたものなのか定かではありませんが、日本で一番古い提灯の文献は応徳2年「朝野郡載」に見えてきます。(900年前の平安末期)
江戸時代以前の提灯は主として天皇家・貴族・武家・僧侶の上流階級で使用され、本格的に庶民が宗教的儀式のお盆や日常生活の照明器具として使い始めたのはローソク(従来は油)が大量生産になって安く入手できるようになった江戸時代以降のようです。
上流階級の提灯の使い方は、従来の松明に替わって紙と木の覆いをつけた灯台、あんどんのように実用品としても使っていましたが、多くは宗教的祭礼や儀式として石灯籠・釣灯籠・切子灯籠を仏前に供える献灯具となっていました。






